1994年『〈日本語学習者のための〉新しい日本語文法』
大修館書店 月刊『言語』1994年12月号P.102〜

一 祈る日本語教師
「動詞の-u形(以下「スル」)が、現在形か未来形かは動詞によって異なる。-タ形(以下「シタ」)は過去形である。ただし、『駅に着いた時また電話するね』という時の『着いた』は、シタであっても過去形ではなく、また、『すみません。さっき私、明日の会議、四時からなんて言っちゃったんですけど、五時からでした。すみませんでした』というときの『五時からでした』も過去形ではない。このような例外は数多く存在するが、それぞれについては、専門的な文法知識が必要となるので、今教室ではあえて触れない。」このように教わった学習者は、とりあえずスル・シタは、英語と同じテンスによる語形対立であるということを学習することになるのだが、教師がちらりと触れてくれた「例外」とやらを忘れてしまわない限り、それに脅えながら日本語を運用して行くことになる。そして教師の方はといえば、学習者が超人的に鋭敏な勘をもって正しいスル・シタを習得してくれることを、職務に忠実であればあるほど熱心に、祈り続けることになるのである。
本稿は、祈ってばかりもいられないと思った日本語教師が、日本語文法とは案外簡単な原理に基づくものなのでは、という模索を始めたその第一段階である。
二 日本語を支える主観的な視点
(1)「行く/来る」の視点客観的には同じ事象を表す「行く/来る」という動詞は、発話者である認知者が自己の主観的な視点を基準にすることで、それが相異なる事象であることを識別し、それによって一方の語が選択される。
(2)「やる/くれる」の視点
客観的には同じ事象を表す「やる/くれる」という動詞は、発話者である認知者が自己の主観的な視点を基準にすることで、それが相異なる事象であることを識別し、それによって一方の語が選択される。
(3)「これ/それ」の視点
客観的には同一の座標にある事象をも指しうる「これ/それ」という指示詞は、発話者である認知者が自己の主観的な視点を基準にすることで、それが相異なる座標にある事象であることを識別し、それによって一方の語が選択される。
認知の対象となる事象がどのようなものに変わっても、誰もがそれを絶対の基準とすることのできる「常に変わらない視点」というものがあるからこそ、それを基にした認知行為の表明であるところの言葉によって、正確な意志の疎通が可能になる。
(1)〜(3)の各類義語事項においては、「常に変わらない視点」すなわち「主観的視点」ということになるが、この「主観的視点」を識別の対象であると考えることによって説明が可能になる文法事項や類義語事項は、おそらく相当な数になる。日本語にはどうやら、発話者の主観的な視点を絶対の基準にしての語彙体系が存在し、さらに文法体系にも、あるいはこの基準が原理となって存在している、ということも考えられる。
三 認知の中枢
「何となく違うんじゃないかと思えてくる」等と言うのは、思考や感情の中枢で起こる事象を、認知者内部のさらに“核”に当たるところにある動かぬ視点からみていることを表していると考えられる。認知の対象となる事象がどう変わっても、視点が認知者内部の核に据えられていれば、——そこではあらゆる事象の影響を受けないであろうから——主観的な視点が不動、不変であり続けることも可能になるのである。この不動の主観的視点を、本稿では「認知中枢」と呼ぶことにする。例えば我々が「来る」と言う時、それは、この語によって言い表されるところの変化ないし移動が、認知中枢に比較的遠いと認識される座標から、比較的近いと認識される座標に向かうと認知される時である。「行く」と言う時には、その方向が反対になる。
「やる/くれる」も「行く/来る」と同じように、相反する二通りの方向のどちらか一方が認知されることによって語が選択される。
四 内と外
認知者は、ある特定の領域をここは自分の領域だと認識することがある。その時自分の領域(以下「内域」とする)が決まれば、当然同時に自分のでない領域(以下「外域」とする)も決まる。内域がその範囲をどこまでとするかは、認知の対象ないし形態等によって変わるのだろうが、さしあたり、不動の認知中枢を中心点とした同心円と考えておく。以下に幾通りかの内域を見る。
(1)「そのこと/そんなこと」の内域
「なにい?豚が空を飛んだ?[その/そんな]馬鹿なことがあるもんか。」という文では、必ず「そんな」を取ることになる。この場合、[内域=発話者の把握している領域]と考え、「そんな」が指すのは常に外域事象である、とすれば説明ができる。
(2)「する/してしまう」の内域
「してしまう」という言い方は、無責任な感じがすることがある。この場合、[内域=発話者の本意や意向の範囲]と考え、言い換え可能な「する」に対する「してしまう」は外域事象である、と説明できる。
(3)「言う/言いそう」の内域
「《動詞連用形》+そうだ」の文型は、[内域=発話者自身の意志、意向による制御の及ぶ範囲]と考え、《動詞連用形》の部分に使用できる動詞は、外域の事象を指すものに限られる、と説明できる。例えば、「秘密って言われたけど、誰かにうっかり言いそうだ」という時、この「言う」は、発話者自身の行為ではあるが、発話者自身の制御の及ばない領域、つまり外域の事象として発話されていれば文法的に正しい。
五 「来る/来そう/来るみたい/来るかもしれない」
競馬の予想で、一着になると予想される馬を一頭取り立てる時、「この馬が…」に続く語として、(1)来る、(2)来そう、(3)来るみたい、(4)来るかもしれない、…という四通りの発話があるとすると、認知中枢にもっとも近いのが(1)で、以下(2)(3)(4)の順で次第に認知中枢から遠くなる、という説明が可能なようである。少なくとも客観的基準はここにもない。六 do/did の境界線とスル/シタの境界線
「現在形」「過去形」「例外」といった調子の、冒頭で見たような説明では、平凡な学習者は混乱するか、誤用を続けるかのいずれかである。[図1][図2]は、一見同じ形をしているようで、実は異なる現れ方をするから同一ではない。英語学習者は、テンスという範疇を学習して do と did の区別を覚える。テンスという範疇の習得によって、 do と did の境界線をわかりやすくまっすぐに引くことができるのである。
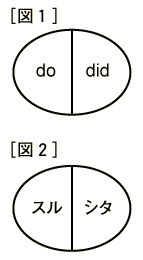
七 スル/シタの範疇
事象の発生・存在がない認知中枢を内域とし、それ以外の領域(事象の発生・存在がある領域、以下「事象域」とする)を外域として、説明を試みる。(1)内域主導の認知「スル」
外域の(現実の)事象の発生・存在を認知するしないにかかわらず、外域に対して内域の方が主導的な関係にある認知形態を表す語形がスル(動詞は「-u」/形容詞は「-イ」/名詞・形容動詞は「-ダ」)になる。
この認知形態は、事象の存在しえない認知中枢が発する関与あるいは指令が、事象域の事象の発生・存在に対し主導的であるため、「行く/来る」の「行く」に似た方向性をもち(図3)、一連の認知行為が完結しない。
このような発話語形スルに現れる認知形態は、認知者が事象の発生・存在を請け合う認知形態であると要約できそうである。以下これを「請合(うけあい)」と呼ぶことにする。
(2)外域主導の認知「シタ」
外域の(現実の)事象の何らかの形での発生・存在を認知し、内域に対して外域の方が主導的な関係にある認知形態を表す語形がシタ(動詞は「-タ」/形容詞は「-カッタ」/名詞・形容動詞は「-ダッタ」)になる。
この認知形態は、事象域の事象が認知中枢に対し主導的であるため、「行く/来る」の「来る」に似た方向性をもち(図4)、受身的で完結的な認知形態である。
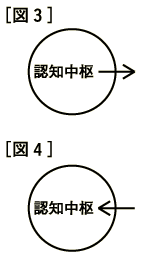
このような発話語形シタに現れる認知形態は、認知者が事象を受け止める認知形態であると要約できそうである。以下これを「受止(うけとめ)」と呼ぶことにする。
以上述べたような認知形態、および文法範疇を、便宜上「請合受止」としておく。
八 テーブル上の小さな饅頭
「請合受止」はテンスと異なり、発話者である認知者が客観的な視点に立たないため、同一の事象に対しても相異なる語形が同時に現れうる。これを次のような例で見る。テーブルの上に小さな饅頭があって、人物は、そのテーブルについている。饅頭の横にはお茶も用意されている。
認知者であり発話者である我々は、人物が饅頭を取ろうと手を伸ばしはじめた時点から、饅頭を食べ終わった後、お茶を飲む時点まで、一部始終を見守っている。その過程で、我々傍観者が、「食べる」あるいは「食べた」を発話しうるのは、どの時点であるか。
まず間違いなく、全過程の全時点で「食べる」「食べた」両方の語が発話可能であろう。まだ口に入れていないうちから「食べたな、これは。」とか、「食べた食べた。これで間違いなく食べた。」等と言える。これは、発話者が事象を受け止めてしまっていることの表明であるからだと説明できる。つまり、事象が完結していなくても認知行為を先に完結させてしまっている、ということになる。
また、食べ終わってお茶を飲んでいる時点で「食べるねえ。思った通りだ。」とか「食べるよ。誰だい食べないなんて言ったのは。」等と言える。これは、発話者が事象を請け合っていることの表明であるからだと説明できる。つまり、たとえ事象が完結していても、発話者の認知行為はこれでおしまいとはならず、認知されているこうした事象は発話者に追従するようにまだ発生・存在するということを表明していると説明できるのである。
九 シテイル
シタは、認知された事象がたとえ現実の事象の認知であったとしても、その一連の認知行為は完結しているため、「現実の事象であり、なおかつ事象の発生・存在を請け合う」ということを発話によって確かに伝えようとするには、シテイルの語形が必要になる。ここで使用されることになる動詞「いる」も、スルの語形であることに変わりはないから、語義そのもので現実の存在を表し、語形で請合を表すことができる。一〇 見えない文法
以前台北で、「日本語に文法はない」と断言されたことがある。断言したのは、日本統治時代に日本語を学ばれたご年輩の男性。日本語教師として駆け出しの筆者は、それに反論できなかった。それどころか、半世紀前から日本語を学習している大先輩のその言葉に、一筋の真実を見た思いすらした。我々は、たとえあっても見えない文法を、一日も早く見えるようにしなければならない。(おきつあきら・日本語教育)
講座スケジュール
| 講座 | 時間数 | 受講料/1名 | |||
| アンガーマネジメント基礎講座 | 80分 | 5,000円 | スケジュールを見る | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アンガーマネジメント講座「思考編」 | 4時間 | 15,000円 | スケジュールを見る | ||
| アンガーマネジメント講座「理解編」 | 4時間 | 15,000円 | スケジュールを見る | ||
| *どの講座からでも受講可 *受講料(教材費込・税込)は当日教室にてお支払いください *教室定員12名 先着順締め切り | |||||






